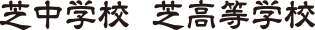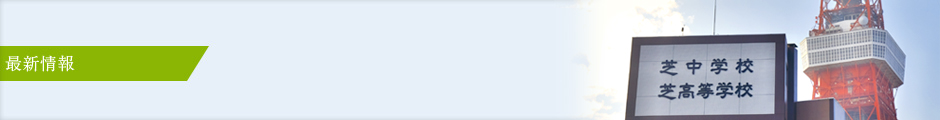武藤校長による『芝漬流子育て』 vol.9
9本目となります芝漬流子育て論『中2までは子どもの生活サイクルに付き合おう』ご覧ください。
中学入学で親は両手を離していませんか?
中学に入学すると、「これで少しは手が離れるかな」と肩の力が抜ける親御さんも多いのではないでしょうか。
特に中学受験を伴走してきたのなら、なおさらですよね。
今や日本の中学生のスマートフォン(スマホ)保持率80%以上ですから、入学と同時にスマホを与え、
多少離れていても連絡も取れるし安心、と子どもにさまざまな判断を任せることも増えるでしょう。
しかし、気づかないうちにすべてを子どもに委ねすぎてはいないでしょうか?
電車通学になったり、スマホを持ったり、新しい環境・友人・学校での生活が始まったりと、
大きな変化の中で急に手を離されたら、子どもたちはいきなり自分で生活のリズムを整え、主導権をもって過ごせるでしょうか。
私は難しいと思っています。
「子育て四訓」でも「少年は手を離せ、目を離すな」とありますが、急に両手を離してしまっては、子どもだって戸惑ってしまいます。
時間管理の目安に、「8−8−8ルール」
子どもが小さい頃は、起床や睡眠、食事のタイミングなど、自然と親が子どもの時間軸に合わせて動いていたはずです。
しかし、大きくなるにつれて、親の時間軸に子どもを合わせるようになってきていませんか?
徐々に大人になっていくとはいえ、第二次性徴や心身ともに落ち着いてくる中3になるまでの中1、中2の間は、
子どもの時間軸を改めて大事に生活をしていただきたいと思います。
私はよく「8−8−8ルール」で生活をするのが理想的と生徒たちに話します。
8時間の学校や仕事、8時間の余暇、8時間の睡眠という〈バランスのとれたサイクル〉が生産性を高める時間管理術とされているからこそ、
学校の8時間、余暇の8時間をどう過ごすのか考えてほしいからです。
そして、この8時間の睡眠も重要なのです。
6時ごろに起きるのであれば、10時過ぎには寝ないといけません。
それなのに、最近は部屋にこもってスマホを見ていて、親が子どもの就寝時間を知らないとか、スマホの利用時間を知らないということが起きています。
深夜まで起きていると、朝起きられず、食事もとれず、体調も優れない。
そうなると、授業や友人関係もうまくいかず、再びスマホやゲームに頼ってしまう――そんな悪循環に陥ることもあります。
スマホルールも片付けも、親が手本に共に取り組む
中1や中2のうちは、ご飯の時間、寝る時間、お風呂の時間などを親が声をかけて、
できるだけ親もその生活サイクルを守ってあげる方向でサポートしてあげてほしいのです。
夜や食事の時は、大人も一緒にスマホをやめる。
子ども部屋での勉強は、中3くらいになってからでも遅くないかもしれません。
最初はリビング学習にして、生活サイクルが自分できちんと守れるようになってから、個室を与えてもいいのではと思うほどです。
時間を守るのも、スマホルールを実行するのも、部屋を片付けるのも、親が手本になりながら一緒に取り組んでいただきたいです。

子どもはよく見ています。
リビング学習をさせるなら、テーブルはスマホも置かず、ご飯の後はすぐ片付けてきれいにしておかなければいけません。
親が「面倒だな」と感じているうちは、子どもが自分の部屋を進んで片付けるのは難しいでしょう。
目を離す前に、子どもが一人で歩けるサポートを
一方で、子どもに任せてほしいこともあります。
それは、子ども同士の学校でのトラブルです。
もちろん大きなトラブルであれば親が介入することもあるかもしれませんが、
些細なことや、まだ関係ができていないから起こってしまうようなことは、まず見守ってください。
親同士のSNSでのやりとりが、かえって子ども同士のトラブルを大きくしてしまうこともあります。
また、自分の子どもの言い分だけを信じて事実確認を怠り一方的に相手を責めたり、先生や相手の悪口を子どもの前で親がまくし立てたり……。
そういうことが起きてしまうと、子どもは本当のことを親に言いづらくなりますし、自分で人間関係を作っていくことが難しくなります。
子どもの多少のトラブルは、子どもの話を受け止めたうえで、少し距離をとって見守る姿勢も大切です。
そして、悩んだり迷ったら、学校にご相談してみてはいかがでしょうか。
それよりは、子どもがスマホをどんなことに使っているのか、お金を何に使っているのか、友達とどんな関係を築いているのか、
何を食べているのか、子どもがどんな服装で出かけているのか、そういったことをよく観察してほしいのです。
日々の様子に目を向けていれば、小さな変化にも自然と気づけるはずです。
そして、基本に戻り、子どもの食事、服装、睡眠時間を改めて見直してみてください。
生活習慣が整わないままでは、生活のリズムを崩し、不登校などにつながることもあります。
先ほどの「子育て四訓」ですが、少年の続きは「青年は目を離せ、心を離すな」です。
目を離す時が来るまでに、子どもが自分で生活を整え、人間関係を築く力を育んでいく
――そのためにも、中学生期の親のサポートは欠かせません。
学校説明会は、低学年の保護者の方も大歓迎です。子育て四訓を実践する教育をぜひご覧になってください。。
第15代校長 武藤道郎